Sports fishing information service japan 1976.3. 九州磯釣連盟北九州支部 海洋磯釣倶楽部 musick 懐かしいパリ (ポール・モーリア) № 6

| 「来たときよりも奇麗な釣り場」 九州磯釣連盟 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 会員のモットである |
Sports fishing information service japan 1976.3. 九州磯釣連盟北九州支部 海洋磯釣倶楽部 musick 懐かしいパリ (ポール・モーリア) № 6

| 「来たときよりも奇麗な釣り場」 九州磯釣連盟 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 会員のモットである |
![]()
![]()
ジャパニーズフィッシング文化と釣り場環境美化推進 そのアジェンダ 未来へ継ぐ釣り文化、釣り場美化推進のとき |


第五章 地球環境を意識したエコ社会と 釣り具業界の取りくみ
マルキュー株式会社 自然環境に対応するエサ作りの原点 (1) その14
私達が直接的に関わる釣りエサは、ほとんど活エサですが、その歴史は数百年以前からあったそうです。
釣りを覚えたての40数年前の私は、虫エサを北九州市小倉砂津海岸で掘ったことや、若松区洞海湾など、干潮時ちょっと掘ったらゴカイや本虫までも良く取れました。その虫エサでクロ、チヌ、キス、カレイ等、なんでも釣れた良き時代でした。その中でも磯釣り師が湖産エビとか藻エビ、桜エビ等の様々な生きエサから冷凍エサを活用して大戦果を上げていましたが、南洋漁場で取れた赤アミ(ジャンボアミ)とか沖アミが大量に市場に出まわると、一気に磯釣りブームが沸き起こり、釣り人口二千万人といわれる昭和50~60年代に入ります。
私も、この時代から磯釣りを覚え、ジャンボアミ(赤アミ)をセメント袋に一パイ、二ハイと持ち込み<、磯釣りを良くしたものです。しかし、そのジャンボアミが解けると、ビチョビチョになるので、マキエがしにくい分けです。
まだこのときは現在のような集魚剤はありません。そこで考えだしたのが福岡県田川郡の向井吉夫先生が発案した米ヌカだったのです。米ヌカは玄米を精米すると、できるものですから、JA・農協等で大量廃棄されます。これをタダで貰いジャンボアミに混ぜ込むと、米ヌカがその汁を吸い込み、しっかり固まりマキエがしやすくなりますから先生のアイディアは大ヒットとなりました。その後、釣り人の要望に応じた現在のような集魚剤が次々発売され便利になりました。紹介するマルキュー株式会社は元来、味噌、醤油等、麹酵母を利用した家庭用食材調味料を生産販売する会社で、今年百年になる伝統のある会社です。その会社が釣りエサ、集魚剤を手掛け始めて半世紀になるそうです。私は九州育ちで、九州のことしか分かりませんが、関東、東北方面の釣りの歴史はもっと古く、様々な生いたちがあり、マルキュー株式会社もそのような歴史の中で釣りエサとの関わりを育んできました。その中で、私が知るところだけを紹介します。


昭和50年代に入り、月刊 釣ファンとか九州磯釣連盟、組織スタッフの方々と親交を始めた20代の私は、向井吉夫先生が所属する上田川磯釣クラブの大会に4~5回参加しました。その中で、山口県向津具半島の油谷湾大浦沖のイカダ釣り大会に何度かゲスト参加したことがあります。
イカダからダゴチン釣りで巨チヌを狙うとか、ウキふかせ釣りでクロ、サンバソウ、ヤズを狙う釣りを始めて知ります。特に興味を持ったのがダゴチン釣りです。付エサを包み込んだ、ダンゴを底に落とし、サシエサを置き、チヌを呼び込み食わせる手法です。この手法を教えてくれたのが九州磯釣連盟 北九州支部の菅沼定雄さんでした。彼は支部の審査部長をしていた方で、月刊 釣ファンの常任熱筆者でもあります。
この釣り方、スタイルで巨チヌからマダイなど様々な魚が釣れて大反響を呼び、各地域でイカダ釣りが大盛況を向かえたのがこの時代です。もちろん私達の釣りクラブもイカダ釣りをけっこうしました。そんなイカダ釣りブームが近年寂しくなってきました。それはイカダ下の海底がドブ底、ヘドロ状になり魚が住み着かない状況になってきたからです。
沖のイカダは元来、マダイ、ハマチ等を養殖する場であり、そのイカダを利用した釣りイカダは営業的な釣り場です。その海底に養殖エサの残りカスとか、釣り人が持ち込んだ赤土から集魚剤等の残りカスが、積もり積もってヘドロ状になり、赤潮の発生原因にもなっているのです。
その為、養殖漁場が少なくなったり、さらに沖に移動する等して試行錯誤しているのが現在の有り様です。又、各地域の港や波止等の釣り場においても、釣り人の増加から大量のマキエで釣り場が荒れてきている惨状は釣り人自身が良く知るところです。
そのような釣り事情を踏まえて、釣りエサから、エサ加工、集魚剤の製法で「もっと自然に優しいエサを作る」ことを理念にして、研究開発しているマルキュー株式会社の取組みを紹介してみましょう。


環境に優しい釣りエサの開発
美しい自然環境があってこそ味わうことのできる釣りの楽しさ。その自然環境を優しくガードしながら、釣れるエサ作りを研究開発しているマルキュー株式会社は、他の会社にない「専門プロジェクトチーム」に大学校があり、公共機関から更に諸外国チームにいたる広い分野まで含めて環境保全に至る実験、調査をたくさんの時間をかけ実施しています。その研究調査報告レポートを、ここで紹介すると数百ページに及びますから、簡単にふれます。


魚に食べられた釣りエサの環境負荷は
東京海洋大学、海洋生物資源学科教授 農学博士 佐藤秀一先生によるレポートでは「エサは水中でどうなるのか」そのテーマで研究をしています。先生の研究チームは主に「環境に優しい養漁飼料の開発」ですが「環境に優しい釣りエサ」についての研究もおこなっています。「釣りエサ」はプラスチックの擬似エサから生分解性プラスチック等、様々なエサがありますが、今度のテーマは「魚に食べられるエサ」です。そのエサは魚用飼料とか釣りエサにして、魚に摂取され消化代謝され糞や尿として排泄されます。そこで問題となるのが
①エサが完全に魚に食べられ、残らないのか
②食べ残されたエサはどうなるのか
③魚に食べられたものは、どの程度消化され排泄されるのか


魚に食べられたエサは窒素とリンになる
①については、魚が完全に食べることはなく、残ったエサを海底生物がかなりの部分で食べていること。
②については、マルキュー株式会社と海洋大学校、海洋環境科学機能材科化学研究室との共同研究により、水中のバクテリア(微生物)によって分解されていることが確認されていること。
③については、魚の胃や腸で消化分解、吸収され、残りは糞として排泄されます。その多くはアンモニアとかミネラル、リンも環境負荷の要因となるそうです。しかし、それらも海水塩分の中で消滅され、プランクトンとして分解してゆきます。
釣りエサの環境への影響は少ない
大学とマルキューの共同研究でグレパワーV9と所定量のオキアミをブレンドしてベレット状にし、凍結乾燥したものをマダイ稚魚等に12週間飼育し、データーを作り、環境負荷を調べたところ、ごくわずかのリンと窒素があるとの結果でした。研究チームが発表した細かな数字は、とっても難しいものですが、釣り人に分かりやすく表現されたグラフがあります。


釣り場の環境の変化も調査
釣りエサが完全に魚、あるいは他の動物、生き物が残らず食べてくれたら環境負荷となるリンと窒素が無くなるのですが、まだ完全な「環境に優しい釣りエサ」についての答えはでていません。その中で合同研究チームは東京湾の三宅島、あるいは伊豆半島の釣り場において更なる環境調査研究を続けています。そのことを更に詳しくレポートが綴っています。 つづく
| ジャパニーズフィッシング文化と釣り場環境美化推進そのアジェンダ 未来へ継ぐ釣り文化、釣り場美化推進のとき |
第五章 地球環境を意識したエコ社会と釣り具業界の取り組み
マルキュー株式会社 魚達などから食べられるエサ、
集魚剤の開発と調査探究(2) その15
(公益財団法人)日本釣振興会で発刊されている「日釣振だより」の中で「釣りの科学」というテーマで、私達にメッセージを書いている奥山文弥先生は東京海洋大学、客員教授ですが、先生は釣り大好き人間で有名な方です。
その先生が同大学とマルキュー株式会社の研究チームのリーダーとして活躍されていますが、その中の一つのテーマが「釣りエサが環境に及ぼす影響」としたレポートを現場から報告されています。
魚に食べられなかった釣りエサの行方 海底からの報告
◎「釣り場に潜って海底を見る」
合同チームは現場から釣りエサがどのようになっているのかを海底から見る調査を7年継続しておこなっています。 その場所は伊豆半島、赤沢港の海でおこないますが、釣り場は関東でも有名な場所で、連日大勢の釣り人が入る好ポイントで知られています、その中の調査です。
◎「釣りエサは海底に残らない」
調査するスポットはダイバー達も多く、メジナやニザダイ、カワハギ、ベラ族が多く居ます。又、釣り人のマキエも多く入りますが、海底に着くまでに魚達から食されている現場ですから、研究チームは海底に「グレパワーⅤ9」と「沖アミ」をブレンドペレット状にした塊を大きく入れます。それを魚達がどのように食し、消えてしまうかなどを、数日かけて観察調査する分けです。
①その塊に最初に群れたのがメジナ、ニザダイ、カワハギ、ベラ類。
②次の日は塊が消え、ヤドカニ等の貝類が集まり、ほとんど食べつくされていました。
③そして最終的には微生物等によって奇麗に食べつくされ、釣りエサの推積は消滅されたレポート写真、映像があり、研究発表されました。そのような研究、調査を繰り返しながら、釣り人のマキエがどのように自然界で消費されるのかを、あらゆるテーマの中で研究報告されています。
釣りエサは環境にローインパクトであるべき 奥山文弥先生の提言
先生は日本国中の、たくさんの釣り場を潜り、海中の環境を多くの仲間の皆さんと調査されています。その中で先生のレポートを一部紹介しますと
①根掛かりした仕掛け、特にエギやそれを繋いでいるPEラインが多く目立っていること、その中でナイロンラインは海水塩分を吸い、時間をかけ放置されると強度が低下し、グローブをした手でも簡単に切ることができます。しかしPEラインは中々切れないそうです。できるならナイロンラインを多用したい。
②釣り人は海や川に対して、もっと優しくあるべきで、タバコや空き缶、釣り具パッケージ等、自己のゴミを放置することなどゴミの持ち帰りをお願いしたい。特に海底の中にこれらのものがすごく堆積してある。
③「釣り人は自然環境に対してロ―インパクトであるべき」という信条を釣り人全員が持ってほしい、その上で「釣り人が増えると、釣り場の環境が良くなる」という社会現象が望ましい。
④今後、地球温暖化の影響で海水温の上昇が始まり、海の中がどんどん変わります。私達の合同研究チームに於いても、環境変化から、「お魚が増殖される豊かな海が得られる釣りエサとの関係」をもっと調査研究し、マルキューの製品に活かし、地球と水辺環境に優しい釣りエサ作りと社会貢献を期待します、と、レポートは結んでいます。
赤土など、海底に残るマキエサは使わない
昔はイカダ釣りとかダゴチン釣りでは、比重の重い赤土とか石粉、砂を利用した集魚剤を多く使っていました。そのことでイカダ下の海底は、それらのものが集積され、又、養殖エサの残りカス等と混ざり、ヘドロ状になってしまうことで赤潮の発生要因にもなり、大きな問題が発覚しました。
その事を反省し、ダンゴ等の練りエサ、集魚剤も含めて、自然に分解されやすいものへとシフトされ、市場も、環境に優しいすぐれたものしか取り扱わない体制となりました。
◎釣り場での赤土、マキエ規制
それらのことを踏まえて、漁協や海釣り公園施設なども厳しく釣りエサを規制し、厳しいところは集魚剤を全面禁止するところもあります。沖アミ、ジャンボアミだけのマキエ、あるいはイワシ等の魚ミンチだけを利用する釣り場もあり、最近の有料海釣り施設は様々なアイディアの中で、釣り人が、お客様が、楽しんでもらえることを大切にしながら末永く営業する為の工夫をしています。
そのことをトータルで考えると、やはり自然を大切にしたエサであり、集魚剤を選んで使用することも大切です。
熱帯魚が増えた海
九州各県から沖縄県、山口県、四国方面まで釣り遊んでいる私にとって、海の変化、特にお魚さんの住変わりはすごく興味があります。その中で私達が住む都市近郊の岸壁で暖色系魚が増えていることに気付きます。
沖縄県の海は熱帯魚の宝庫ですが、その沖縄の海でしか見られなかったブルーや黄、白、緑、赤色の小さなお魚さんが大分県蒲江、鶴見半島の港廻りに今、増えています。又、北九州市、関門海峡の岸壁にも、そのようなお魚さんが住みつくようになり、今まで見た事のない熱帯魚が釣れています。
5~15㎝ほどの色彩やかなお魚さんを釣り、リリースしていますが、10数年前では考えられなかった、水族館で見られるお魚さんを現実に釣るのですから、最近の海は物凄く変化していると想うのです。
地球温暖化と赤潮の関係
福岡県から佐賀県にかけての玄界灘の赤潮発生も、海底資源が南の海、特有の無藻根という、魚が住みづらい砂泥地帯に変化しているそうです。南シナ海の島はブルーの海で透き通って海底が見えますが、底が砂泥地でサンゴが多くあるからブルーに見えるのです。
九州の浅場の海には、びっしり藻が密集して、海草、コンブ等の海藻が多くあり当然、海が黒く見えます。そのような海にはお魚さんの住み家から産卵場所としてエサが豊富にあり、魚達の楽園が描けます。
地球温暖化の影響で海がドンドン変化し、魚達が住みづらくなっていることに私達は、環境とかエコまで考えた釣りスタイルを考えなくてはなりません。又、気温が、温水が、ということも現実にありますが、それよりも私達が楽しんでいる釣り場の変化、人々が海岸を汚している、汚染している事も含めて、これから先を考えなくてはなりません。
「地球を大切に」は、エサの革命もそうですが、そのエサを使っている私達も責任を感じながら、これからの釣りを楽しみたいものです。
みなさん、お魚さんを大切にしましょう。食べないお魚さん、小さなお魚さんは、優しくリリースしましょう。そして、釣りマナーアップを、まず私達が率先し、行動し、釣り人のレベルアップを図りたいと思います。
| ジャパニーズフィッシング文化と釣り場環境美化推進そのアジェンダ 未来へ継ぐ釣り文化、釣り場美化推進のとき |
第五章 地球環境を意識したエコ社会と 釣り具業界の取りくみ
㈱オリムピック社長自ら発案した「イエローガイズ」とは その16
グラスロッドからカーボンロッドに変わりはじめた昭和50年代、まだ釣り具業界は安価なグラスロッドが主流。
その頃の磯竿は剛竿であるが粘り腰の強い、反発力がある十分な釣り竿でした。しかし、一般大衆から趣味としての釣りブームを開花させた竿とスピニングリールは釣り人のニーズに応えるべき、より価値観の高いものが次々にヒットされるものでした。
㈱オリムピックの純世紀とかアマゾン、純93スピニングリール等は、釣りを趣味にする釣り人なら誰しも手にしたい代物でした。その株式会社 オリムピック九州営業所、営業マンの大前さんとひょんなことから仲良くなり、インストラクターの肩書きがもらえました。そのテスター会が大分県蒲戸でありました。
東京から、社長自らテスター会に参加。しかも、その会になんと田中釣心先生や現 釣研FG会長、寒竹さん、前会長の磯島さんや、有名な磯マンが10数名も居たんですね。テスター会ですから自前の白い磯竿、インストラクター・センサーグレ1.5号、その磯竿に新しいモデルのスピニングリールをセットしてのテストをおこないました。
イエローガイズの取り組み指針
そのようなテスター会や福岡市のオリムピック九州営業所でたびたび会議がありました。しかし、釣り具モニター販売促進会議は二の次で、会の根本的なスタンスは釣り場環境を意識した、釣り場環境美化促進とエコ社会をイメージした活動、その上で釣り文化の伝承という、とてつもない会だったのです。
「イエローガイズ」とは、そのような地球規模的な活動を、釣りを通して行う主旨であり、社長が発案してアクションプログラムされ、全社的な社員の活動方針となります。その中の私達プロジェクトチームでもありました。まだ昭和50年代の頃にそんな事を言うとか、考えを実行する企業、会社、政治家など居ませんから、今に思えば凄い社長だったのかも知れません。もちろん、そのような活動資金は㈱オリムピックとか、社長自らのボランティア、そして私達イエローガイズのスタッフにも少々重くのしかかってきました。しかし、最終的には社長が代わるまでの6~7年続いたでしょうか。その後イエローガイズ及び㈱オリムピック、インストラクターとしてのチーム活動が無くなりました。
㈱オリムピックが手掛けたレジャーボートチームに、ゴーセンの中山さん
その時代、モータリーゼーションという発想で、㈱マミヤオーピーがモーターボートを手掛けた中に、専任チーフに、前、釣り糸のゴーセン、広告営業部長だった中山さんが、このチームを引っ張ることになりました。その中山さんとは、初代LKGゴーセン・フィルドテスター発起人代表として月刊 釣ファン、河村社長と九州磯釣連盟、都留正義会長以下のそうそうたるメンバーをまとめ、27才の私を投げ釣り部門で誘ってくれた方でした。
その頃より中山さんとの親交が深まり、釣り場環境美化社会のアシストとしての、釣り糸が海中で消える無公害革命分野の研究開発をされた方です。
その後、ゴーセンを定年退職されオリムピック社長と結ばれ。トップダウンとして、レジャーボートを広くPRし、レジャー産業を変革させるアクションがありました。しかしあまりの過剰投資で失敗し、経営が立ち行かなくなります。
今は小さな㈱オリムピック(㈱マミヤオーピー)で運営されていますが、あの頃の志を私達はしっかり受け継いでいると思いますし、専任チーフだった田中釣心先生が(公益財団法人)日本釣振興会 福岡県支部長となり、磯島さん、寒竹さんが釣研FG会長となり、これらの活動をしっかり受け継いでいます。
環境に優しいゴミ袋も土や水で溶ける
私達が大切に使っている(公益財団法人)日本釣振興会より寄贈されているゴミ袋は大、中の二種がありますが、このゴミ袋もエコで製作され、しかも水や土に解ける素材で作られています。釣り糸分野でも環境に優しい釣り糸として、時が立てば海水で消える釣り糸が㈱ゴーセンで実用実験段階にあり、いずれ発表されます。
現代社会の中でも企業努力とか国政による取り組み等で、エコ社会が急速に進化されています。釣り具業界も、これからの地球環境を意識した優しい自然を整える試みを、よりいっそう早足で進めています。
私達釣り人も、そのような企業を応援するとか、エコ製品とか「グリーン購入ネットワーク」会員企業の商品を購入する等、出来るところから協力したいと思います。皆さんよろしくお願いします。
| ジャパニーズフィッシング文化と釣り場環境美化推進そのアジェンダ 未来へ継ぐ釣り文化、釣り場美化推進のとき |
第五章 地球環境を意識したエコ社会と 釣り具業界の取り組み
企業と行政、国政レベルで考える「グリーン購入ネットワーク推進」
それを支える釣り人は その17
テレビで人気の細木数子さんが、ちょっとお休みしているこの頃ですが、ひょんなことから、この方の生き方、考え方、実践を知ることで驚いています。
それは今年7月、福岡県京都郡にある豊津霊園に始めて行くときでした。国道10号、築上町から県道で彦山方面の城井川を上りながら、カーナビで山道を上ること1時間あまり、山並を利用した新しい霊園がありました。
別に私は購入する分けではないのですが、墓所のイメージを勉強中で、いずれ家の墓地を整えることを考えています。その中で、妻と一緒に案内されて行きますと、その山並のふもとに立派な神社があるので不思議に思って聞くと、その神社の所有者があの有名な細木数子さんであること。そして、その山のいくつかを譲り受け森林を守っている!! ことを聞きました。山を持っている地主が開発を恐れ、彼女に寄進したと聞きます。その上で、細木数子さんは全国あちこちで森林の苗を育て、森を、山を、山林を購入して緑を増していることを聞いたのです。そのことは彼女本人が出るテレビ番組とか書籍、雑誌等からでも紹介され、そのことが有名であることを仲間達から後日聞きました。又、朝日新聞8月10日に記載された記事では、埼玉県が推進している「自然再生クリーン事業」は民間のパワーで譲り受けた森林とか土地、財産、寄付金などを利用して、自然界を残す、守る、育てる、試みをアクションプログラムとして、その実績を積み重ねているそうです。私達は自然界を壊すことばかりを考え、育てることを、半分も実行していません。もちろん国策とか政治のパワーでは全く進めていないことを、NPO等の団体・市民とか、企業が政治に先駆けて活躍されていることを多く知っています。その中で、やっと国策のプロジェクトが立ち上がりました。
国と企業が取り組む「グリーン購入法」ネットワーク
地球環境の維持改善の為、環境配慮型の用品開発から製造販売までの環境を意識した商品を広く国民に提供する「企業、会社を支える法」として「グリーン購入法・GPN」が2001年4月から施工されました。
◎「グリーン購入法」とは
環境に優しい商品を製造し、お客様に購入いただくことで環境問題の解決や環境負荷の軽減に役立てようとする法律に基づくシステムです。その法律に基づいて多くの企業が賛同し、積極的に取り組む「GPN」、釣り竿やリール、ウキや、さまざまな釣り道具のパッケージにグリーン商品、規格、JASラベルがあります。
◎なぜグリーン購入か
私達の暮らしに最も身近にある自然は、様々な要因で悪化の一途を辿っています。グリーン購入を社会全体で実践し、拡大してゆくことで環境破壊を即し、保全に直接的に貢献する制度です。
◎地球エコ・アップ作戦とGPN商品
私達の身近で感じているエコ商品から食材まで様々な形で「エコ!!」が叫ばれておりますが、現実には私達の暮らしが豊かになればなるほど地球環境が悪くなるというのは避けて通れない現実です。
その中で今できるところから少しずつ進めること、プログラムする、無駄のある生活をしないとか、浪費しない。それは電機とかエネルギーの消費を少なくすることが直接的なエコに結びつくものです。
例えば、家に太陽パネルを取り付けて電気の節約をする家庭が増えています。釣り場で風車がグルグル廻っていますよね、ソーラーシステムも様々なものに利用されるようになりましたし、釣り具店では、マンガン電池からアルカリ、リチウム、そしてLEDライトの普及で随分と軽くなったり、商品がコンパクトになったりしていますね。これ等も「GPN」商品なんです。


◎地球環境負荷低減目標「マルキュー株式会社の場合」
釣りエサのマルキュー株式会社では環境負荷低減の為、工場からの二酸化炭素排出量を2006年度実績に対し、2011年度までの5年間で10%削減を目標に、ほぼ達成できる確約ができました。又、地球温暖化防止の電機等のエネルギー消費を最新設備の増強から、さらに削減する目標をクリアーさせたこと。又、グリーン購入の推進から生産ロスの改善、さらに産業リサイクル等を全社的に取り組み好成果を上げています。
◎今、釣り具業界においても様々な自社努力を積み重ね、環境に優しい工場設備から、エコ社会を目指した企業がたくさんあります。私達の身近に「GPN」商品の多くは、ほとんど国内で生産されたもので、やや高価なものかも知れません。
東南アジア諸国から多くの輸入品が格安で出廻っている中、安心できる良いものは、やっぱり国産品です。私はそのようなことを踏まえて、できるだけ「グリーン購入ネットワーク推進企画商品」を購入するようにしています。
みなさん、お魚釣りもエコの時代です。どうしたら「簡単にお魚さんがたくさん釣れるか?」そのことを考えながら、釣り具、タックル、仕掛けやエサ等、私達の身近にある釣り用品をもう一度見直し、優しいエコ社会を構築してゆく上で企業努力を促し、それをアシストしながら地球を大切にしたお魚釣り文化を支えてゆきたいと思います。


第五章 地球環境を意識したエコ社会と釣り具業界の取り組み
釣具店とメーカー、そして私達が目指すリサイクル文化とは その18
住み慣れた都会から、ちょっと離れた米(こめ)所の京都平野に住むようになって早12年が過ぎました。
その地域は周防灘の元永山(行橋市)から朝日が昇り、夕日は香春岳(田川方面)に沈んでゆきます。その夕日、水平線上に少々の街並がありますが、家そばには田ンボが広がり、少々歩けば二級川の祓川があり、河口は広い渚でマテ貝が掘れます。それに続く南側は遠浅の浜辺が豊前、豊後へと続いています。いくつもの川水が周防灘に注がれている海岸、渚、浜、そのような地域、そのような田舎暮らし? でもありませんが、恵まれた自然環境の中で生活していると、随分とエコなライフスタイルをしていることに気付くのです。
自然に優しいエコのライフスタイル
まず私家から出るごみは缶とビン、ペットボトルぐらいです。魚などの骨や臓物、野菜の切りクズなどの、いわゆる残飯物は、畑そばに深さ1mほど掘った土の穴の中に入れるのです。一ヶ月ほどで満パイになるので、上から土をかぶせて1年ほど寝かせると堆肥になるようで、その穴を毎月1コずつ場所を変えて掘っています。落ち葉や紙などの燃やすものは畑で燃やすことができますし、植え木などの切り屑とか雑草なども乾かしてほとんど燃やしてしまうことができます。本誌の新聞、雑誌、古着などは、地域の子供会が喜んで持って行ってくれるし、清掃車が持って行くものは全て資源ゴミでリサイクルされますから、我が家から出るゴミは100%自然に返すことができます。ただ、樹木や雑草が多く、草花を美しく整えるには苦労はしますが、畑からとれる自作の野菜は凄く恵まれています。
趣味で始めた家庭菜園とか、お魚釣りも自然環境に優しく、それ相応の恵みを頂けるメリットは凄く大きいのです。しかも趣味の釣りをすることで、すごく地域の人々から羨ましがられます。
釣り具リサイクル文化
週末は半日サイクルの近場の釣りを多くしていますが、特に関門海峡門司や下関、苅田港あたりに良く通っています。
その中で釣りが終わった後、自己のゴミはもちろん周辺のゴミを拾い集め、家で分別してリサイクルするのですが、その中の拾い物に折れた竿、壊れたリール、クーラーボックスやバッカン、釣り人のタックルが随分と多いのです。安価で買える釣り竿も、最近は使い捨て時代なのか、これらのものをゴチャゴチャ集めてリサイクルする友人もいます。釣り竿にはガイドやリールシートが付いているので、この部分だけでも再利用し、新しい釣り竿を作る事ができます。又、カーボン竿には部分的に利用すると、マキエ柄杓も出来るし、ギャフとかタモも出来たり、スクラップ竿の部品取りも出来るので、けっこう組み合わせて別調子タイプで竿を作る仲間もいます。リールに於いても、スプールとかハンドルなどの部品取りから、ちょっとしたアイディアで再利用したり、修理できたりします。
やはり、その道のプロとか、趣味で遊べる釣り人は、けっこう様々なアイディアを持っていますから、利用できる釣り具をゴミにしなくてもイイのに!! と、思いながら釣り場で捨てられた物を見るとガッカリするのですね。
今、流行の中古品ショップ、こちらのお店では90%どんな形の物でも引き取ってもらえます。タダで引き取ってもらっても、その釣り具を誰かが使ってもらえるなら、その方が夢があってすごく嬉しいのです。
捨てるよりは使ってもらえることを考え、又、古い釣り具とか、使わない釣り具など、家中にたくさんあって迷惑している家族が居るなら、いっそのこと思い切って中古品ショップで引き取ってもらってほしいと思います。その上で、プレミヤ物とか、価値のある古いタックルがあれば、更にお得な事だってあるのです。リサイクル文化も最近はエスカレートして、何処でもこれらのお店があり、釣り人の欲求と、こだわり感をプラス趣向にして、様々なスタイルで釣り具業界が進化しています。そのようなことで最近、釣具店で使い終わった釣り糸や仕掛け、ルアーやエギ、スプーン等、使えなくなったリールとか竿を処分してくれるお店が増えました。再利用できるものは良いのですが、使えないものは大量にメーカーが集めてリサイクルするそうです。
私達の生活に欠かせない乾電池や電球、蛍光灯の球を再利用する等、様々な分野でリサイクル文化が定着されました。社会に優しい、地球に優しいリサイクル文化を維持しながら、私達の釣り趣をもっと文化的にイメージアップしたいと思います。ぜひ利用して下さい。
集魚剤とマキエサの効果
私は20数年前から、マキエサに入れる集魚剤は家、もしくはお店でブレンドし、少し寝かせ、時間を持たせることにしています。それは沖アミやジャンボアミのアミ汁が集魚剤に染み込み、さらに付加価値を高める集魚剤に凄く満足しているからです。集魚剤は便利とか機能を持たせる役割もありますが、魚に食ってもらう集魚剤であり、魚からさらに貝、カニ、エビなど、食物連鎖によるプランクトンまで食べてもらい、マキエサが完全に海底から消え去ることを大前提として、マキエサを選びます。その為に出来るだけ沖アミ、ジャンボアミと集魚剤、それにミネラルたっぷりの淡水で練り込んでやると、すごくマキエ効果が大きいのです。このことは20年も前から実践し、出来るだけこの事を大切にして、マキエサ、集魚剤の活用を考えています。
その上で、これらのパッケージが釣具店や家から処分でき、釣り場でゴミが出ない、出さない事を皆で連帯したいと思います。釣り趣を重ね、遊ぶ釣りの中で、たくさんの釣り具、エサが求められ、釣り文化をエスカレートさせていますが、それらの物が大量に消費され、ゴミとなるこの頃、少しでもゴミが出ない、出さない工夫の中で最小限、自然界に返す。そしてリサイクルすることを私達皆で考え、社会に、自然に優しい釣りをしながら楽しみたいものです。
| 第6章へつづく |
| 本文と合わせて1960年代からのポール・モーリアのmusick №1~№15までお楽しみ下さい |
ジャパニーズフィッシング文化と釣り場環境美化推進 そのアジェンダ 未来へ継ぐ釣り文化、釣り場美化推進のとき 地球環境を意識したエコ社会と 釣り具業界の取りくみ |












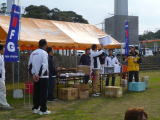





| 北九州市若戸大橋の景観 |








| 北九州関門海峡門司めかり海岸の景観 |
北九州関門海峡門司めかり


和布刈り遊歩道下の釣り場


関門海峡門司めかり大岩


関門海峡門司太刀浦


関門海峡門司田ノ浦


北九州門司少年自然の家
皆さん、九州磯釣連盟に入会しませんか、磯の大物釣りからルアーのヒラマサ、スズキ。シロキスの投げ釣り部門まであります 九州磯釣連盟では、2名以上のクラブ、個人でも参加募集中です。北九州支部エリアは北九州市、筑豊、直方、遠賀、行橋、豊前など。その他の地域でも紹介します。メッセージ、申込みは九州磯釣連盟本部へリンク。私のページでも、ご案内中です、どうぞよろしく。 問い合わせは 九州磯釣連盟・本部事務所・ 福岡市南区老司3丁目18の34 TEL・092 408 5680番、連絡下さい |